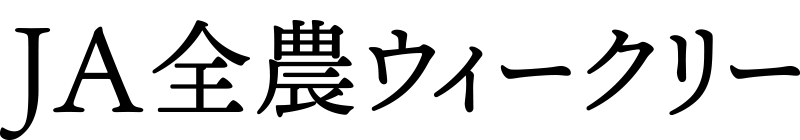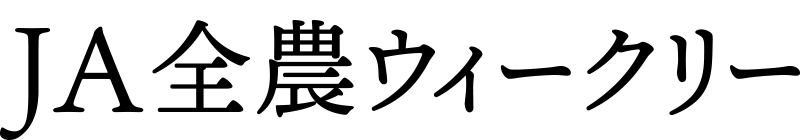持続可能な食と農を海外の政策から読み解く(上)
環境重視型農業と食料の権利
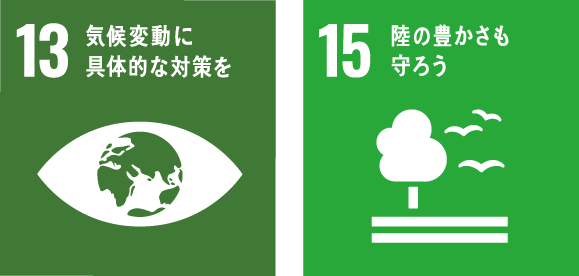 温暖化対策を目的とした脱炭素・カーボンニュートラルは今や世界の農業の潮流となっています。欧米では政策を通じてどのようにしてその実現を図ろうとしているのか。日本の「みどりの食料システム戦略」の実現に向けても大いに参考になります。海外の農業政策事情に詳しい日本農業新聞特別編集委員の山田優氏にご寄稿いただきました。(全2回)
温暖化対策を目的とした脱炭素・カーボンニュートラルは今や世界の農業の潮流となっています。欧米では政策を通じてどのようにしてその実現を図ろうとしているのか。日本の「みどりの食料システム戦略」の実現に向けても大いに参考になります。海外の農業政策事情に詳しい日本農業新聞特別編集委員の山田優氏にご寄稿いただきました。(全2回)
畑に木を植える農家

山田 優(やまだまさる)氏
南仏のオーシュを訪ねたのは4年前。どうしても見たかったものがあった。フランスの農業改良普及員を退職して有機農業を始めたピエール・プジョさん(54)が、畑に木を植えているという話を聞いたからだ。以前、彼が訪日した際に埼玉県小川町の有機農家、金子美登さんの農場を案内した縁があった。
効率を求めれば、ほ場は大きい方が良いに決まっている。大型農機の普及に伴ってフランスでは畑を区切るヘッジと呼ばれる石垣や生け垣、立木を取り払った。畑1枚当たりの面積が大きくなり、大型トラクターが走り回ることで生産性は大きく向上した。
なぜ、プジョさんは効率とは逆の道を選んだのかを聞いてみたかった。
なだらかな斜面に広がる210haの畑には、一面にカバークロップと等高線に沿って数十メートル幅で苗木が植えられていた。
プジョさんは、私を隣の畑との境界に連れて行くと、地面に腰掛けた。隣の畑に比べ、プジョさんの畑は30cmほど高かった。
「僕が就農して4年。土壌の浸食を防ぐ効果がはっきり出たよ」
土を耕さず、カバークロップで表土を守る。さらに植えられた木々が育てば、風を遮り、植生や昆虫など生物多様性が豊かになる。自らの農業の夢を語っていた。
今年の8月半ば、プジョさんを案内してくれたフランス・アグロフォレストリー(農業森林)協会のファビアン・バラゲ国際部長に電話で話を聞いた。
「ピエール・プジョさんの畑の木は、4m近くまで生長した。おかげで畑は豊かな生物相となり、彼の試みは大成功だよ」
私が訪れた時と風景は変わったようだ。畑は森と複雑に絡み合い、しっかりと地域の環境の中に溶け込んだという。
この4年間に変わったのは、プジョさんの畑だけではなかった。
「フランスはもちろん、欧州全域でアグロフォレストリーは爆発的に増えているよ」
電話の向こうでバラゲ部長は興奮気味に話してくれた。
欧州農政の大転換
追い風になるのは、欧州農政の大転換だ。欧州連合(EU)は2020年、地球環境対策強化の一環として、農業分野で大胆な方針を打ち出した。ファーム・トゥ・フォーク(F2F)戦略と呼ばれる。農薬・肥料の削減や有機農業の大幅な拡大のほか、地球温暖化対策などが盛り込まれた。EUは世界に先駆けて農業の新しい国際基準を決めると意気込む。
これからF2Fを欧州共通農業政策に具体策として落とし込む作業が始まる。同政策はまんべんなく農家を支援する政策から、環境政策への色彩を強めたのが特徴。農家に支払う補助金の4割は、環境に役立つことを条件に支払われることになる。
アグロフォレストリーは(1)二酸化炭素など温室効果ガスを木に貯蔵(2)生物多様性を豊かにする(3)農村の景観を改善するなどの効果がある。EUは、一律に1ha当たり100本を上限としていた農地の植林基準を見直すなど、アグロフォレストリーの規制緩和をして後押しする計画だ。
「出番が来た」とバラゲ部長らが期待に胸を膨らますのは当然だろう。
納税者の視点を意識
 なぜ、F2Fのような環境重視型農政が生まれてきたのだろうか。
なぜ、F2Fのような環境重視型農政が生まれてきたのだろうか。
21世紀冒頭に、欧州農業政策の大改革を成し遂げたフランツ・フィシュラー元EU農業担当委員を2018年、彼の出身地であるオーストリアのインスブルックに訪ねた。
――欧州共通農業政策は農業者の支援から環境対策としての側面を強めています。
「国家にとって農業や農村は大切だが、農業者イコール弱者ではなくなった。農村に多額の予算をつぎ込むには、納税者が納得するだけの理由が必要だ。それが環境問題であり、アニマルウェルフェアだ」
――納税者を意識することが大切になってきたのですね。
「補助金を支払うには目的をはっきりと説明できることが重視されるようになった。共通農業政策が残るためには、納税者の視点がますます重要になるだろう」
フィシュラー氏の予言は、F2Fとなって、現実の欧州農政に反映されたように見える。
環境問題には冷淡な態度を取り続けたトランプ氏から、バイデン大統領にバトンタッチされた米政権も、温暖化対策重視に舵を切っている。政権は休耕面積の大幅な拡大などで温室効果ガス抑制、生物多様性の向上を進める考えだ(※)。欧州とは温度差はあるものの、全米の農業地帯で高温、干ばつ、山火事などの被害が拡大し、農家も環境対策は自分たちの問題だと考えるようになってきた。
実は先進各国とも、自国の農業保護には力を入れている。完全な自由放任の競争で保護を撤廃したら、農業が衰退し、地方経済や食料安全保障に打撃となることを懸念するためだ。農業大国をうたう米国も例外ではない。
日本農業過保護論を批判する東京大学の鈴木宜弘教授の近著(食料・農業の深層と針路=創森社)によると、農業所得に占める補助金の割合は、日本が38%なのに、米国は42%、フランスやドイツ、英国は6割以上(いずれも2012年)と高い。
「日本の農家は外国よりも補助金に依存している」というのは間違い。各国とも都合良く相手国の悪口を言うが、ちゃっかりと自分の所は保護しているからだ。欧米諸国は納税者の目を意識して農政を手直ししつつ、自国の農業保護を持続させるねらいがある。
日本もみどりの戦略
日本では農水省がみどりの食料システム戦略を5月にまとめ、その後、政府全体の骨太の方針に正式に位置づけられた。さらに政府は法制化を計画している。欧州のF2F戦略などの動きに刺激され、「わが国として持続可能な食料供給システムを構築し、国内外を主導していくことが急務」(農水省)という判断で練り上げられたものだ。
これまで生産性向上、生産振興、需給の調整、輸出拡大などを大きな柱にしてきた国内農政に、環境対策を思い切って格上げしようという宣言とみられる。国内の有機農業面積を2050年までに100万haまで引き上げるなど大胆な目標を掲げた。
先進国農政は、音を立てるようにして環境重視型に転換しつつある。日本も遅ればせながらその流れに乗り込もうとしている。農薬・肥料の削減など直面する課題は多く、生産者やJAにとって厳しい内容も想定される。しかし、納税者、消費者の理解を得るための努力を続けることが、求められている。
※注釈)米農務省が1980年代から行っている土壌保全休耕プログラム(CRP)は、河川汚染の防止や土壌により吸収された温室効果ガスの大気放出を防ぐことを目的に、一定の土地を対象に政府が補助金を支払い、農家が作物栽培を止める仕組み。現時点で800万haがCRPにより休耕されている。バイデン政権では新たに160万haを追加する方針。