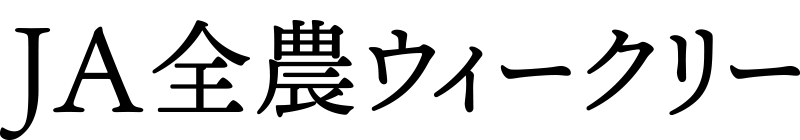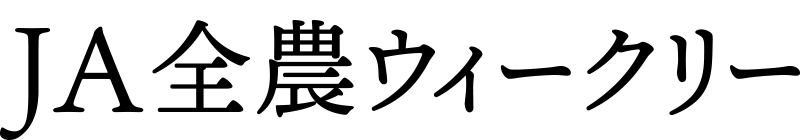コミュニケーション
【WEB限定記事】広島大学×広島県本部 共同研究で現地検討会
2025.09.08
広島県本部
水稲栽培における鶏ふん堆肥の普及・拡大へ期待
広島県本部と広島大学は、2022年度から「水稲栽培における鶏ふん堆肥の有効活用」に向けて共同研究を行っています。8月27日には「全農チャレンジファーム広島・三原農場」(広島県三原市)で、共同研究の取り組みでは初となる現地検討会を開催しました。
JA職員や行政関係者ら約50人が参加し、研究の進捗(しんちょく)状況や、メタンガスを測定するチャンバー(特定のガスや物質の測定、解析のために設計された装置)などでの調査を視察しました。
4年目を迎えた共同研究では、鶏ふん堆肥の施用量が「あきさかり」の生育、収量などに与える影響やチャンバーを用いたメタンガスの排出量などを調査しています。広島大学大学院統合生命科学研究科の長岡俊徳准教授は「鶏ふん堆肥を国内で自給可能な肥料として活用することで耕畜連携と資源循環を促進し、持続可能な食料生産を目指していく」と水稲栽培における鶏ふん堆肥の利用意義を強調しました。
また、広島県本部肥料農薬課の田中海佐子さんは混合堆肥複合肥料入り一発肥料「エコケッコー」を紹介。同肥料は県内で発生した鶏ふんを原料の一部に使用した混合堆肥複合肥料を約25%配合しており、粒状のため田植えと同時に施肥できるのが特徴です。
参加者からは「鶏ふん堆肥を使って水稲を栽培している生産者からは、収量が慣行栽培と同程度だったと聞いている。今後は、生産者も含めた生産者同士で意見交換できる現地検討会を開いてほしい」との声が上がり、今後の鶏ふん堆肥の普及・拡大が期待されています。両者は今後も地域資源を有効活用することで、持続可能な農業経営の実現を目指し、研究を進めていきます。