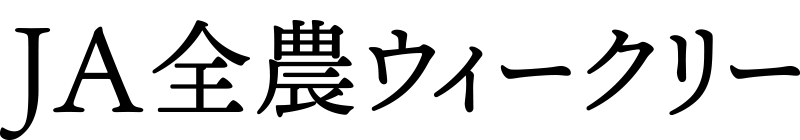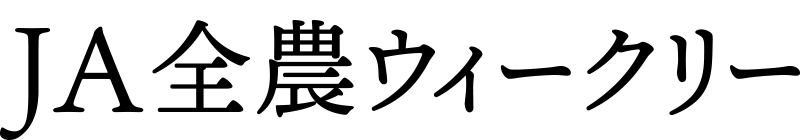【協業パートナーとの特別座談会】ゆめファーム 全農は次のステージへ
生産者の手取り最大化と栽培技術の育成・普及展開をめざす「ゆめファーム全農構想」。今回は協業パートナーであるNTT東日本(株)の熊谷敏昌代表取締役副社長、(株)安川電機の松浦英典理事と全農の安田忠孝代表理事専務による座談会をお届けします。(取材日:6月13日。当時の役職で掲載しています)
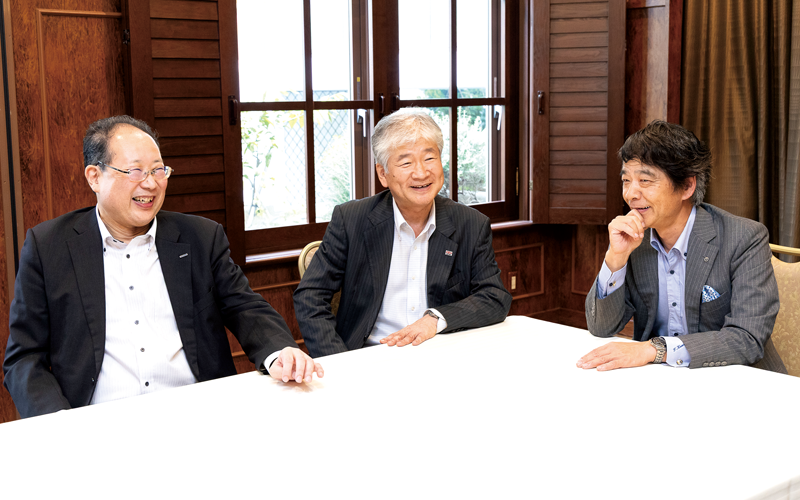
ロボットと通信で農業の未来を拓く
安田忠孝代表理事専務 生産者に生産資材を届けるだけでなく栽培技術と一体で全国に広げたいという思いから、「ゆめファーム全農構想」が始まりました。2014年に栃木でトマトからスタートした後、高知ナス、佐賀キュウリへと着実に歩みを進めています。特に、安川電機様の「ロボット」、NTT東日本様の「通信」といった異分野の先進技術が加わることで、その可能性は大きく広がりました。現在は実証農場での検証を進め、埼玉での「ゆめファーム全農トレーニングセンター幸手」の設置も準備中です。構想には、研究開発・実証・育成・普及展開の4段階で栽培技術を全国に広げるという狙いがあり、協業を通じてようやく育成・普及展開という次のステージが見えてきたところです。
松浦英典理事 「ゆめファーム全農SAGA」で進めるキュウリの葉かき・収穫自動化ロボットの開発では、葉や実の形状が一つ一つ異なるという、従来のロボット開発にはない難題に直面しました。工場のように単調な作業ではなく、変化に富んだ農業現場で使えるロボットを実現するため、10人ほどのパートの皆さまと一緒に1カ月間現場で働き、動きをデータ化し、人工知能(AI)とカメラで学習させることで柔軟に動ける仕組みを作りました。まさに“協働” で試行錯誤を重ねた成果であり、ようやく本格現地導入への道が開けてきました。
熊谷敏昌代表取締役副社長 通信の現場でも「答えは現場にある」とよく言います。私たちも実際に圃場(ほじょう)に立つことで、何をどうデータ化すべきかを見極めてきました。現在、「ゆめファーム全農」において遠隔栽培支援プラットフォームを提供していますが、全農様の専門家が分析したデータを、正確に現場に届ける役割を担っています。このプラットフォームを活用すれば、たとえばキュウリの栽培データがどんどん蓄積されていきます。そうなれば、安川電機様のロボットとの連携も進み、データに基づいた適切でタイムラグがない操作や収穫時期・収穫量の予測と組み合わせたオートメーション化が実現しやすくなります。また、栽培・労働管理サービス「Digital Farmer」の実績データと組み合わせることで、経験と勘に頼らない農業経営は今後さらに加速していくことでしょう。


協業を通じて得た育成・普及展開への確信
安田専務 日本の農業は生産者が減り続け、今の生産力を維持すること自体が大きな課題です。農業者だけでの解決は難しく、外部の視点や技術が加わることで、自分たちの可能性にも気づかされました。安川電機様から「植物は1本1本形が違う」と指摘され、農業における機械設計の難しさを実感しましたし、NTT東日本様の空間を超えた同時指導を可能にする通信技術の遠隔支援も「なるほど、こういうことができるのか」と大きな気づきをいただきました。協業を通じて「私たちにもまだできることがある」と実感し、「これなら育成・普及展開のステージに進める」と確信できたのは大きな転機でした。
松浦理事 最初にロボットを現場に持ち込んだ際、作業の現場の方々に戸惑いや不安の声をいただくこともありました。けれども、しばらくすると「もっと楽に働ける」「別の仕事にも取り組める」と前向きに受け止めていただけるようになりました。ロボットは人を減らすためのものではなく、人をより有効な場所に配置し、現場の力を引き出すための存在という理解が浸透し始めていると感じています。
熊谷副社長 AIやロボットも結局は「使う人」がいてこそ意味があります。それを活用するには知識や時間も必要で、最初は私たちが伴走し、やがて使う人自身が変わっていく。その変化こそ「新しい農業のかたち」への一歩だと思っています。私たちはネットワークの専門家、安川電機様はロボティクスの専門家として、どうすれば「ゆめファーム全農」が最高に幸せな場所になるかを考えて取り組んでいます。


「夢のある農業」をともに切り拓く
安田専務 「ゆめファーム全農」はこれから、実証のステージを経て、いよいよ育成・普及展開の段階に入ります。ここを確実に進めていくことが、今後の大きな課題です。施設園芸だけでなく、他の農業分野にも応用できるかどうかという正念場だと感じています。技術の垣根を越えた今回の協業体験は、人手不足をはじめとする農業の課題を乗り越える上で確かな手応えを与えてくれました。だからこそ、生産システムが縮小する中、「この国でどれだけの生産が維持できるのか」という問いに対し、私たちなりの一つの答えを示していきたいと考えています。「こんな農業なら挑戦してみたい」と思える可能性を示しながら、「夢のある農業」をともに切り拓(ひら)きましょう。